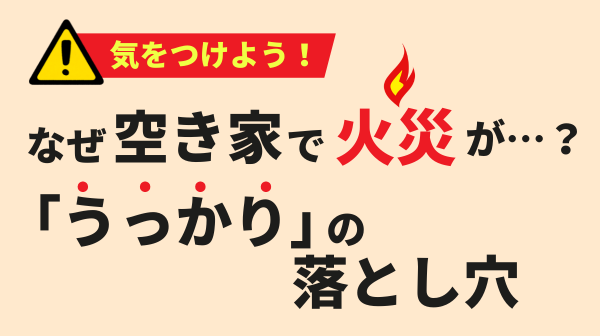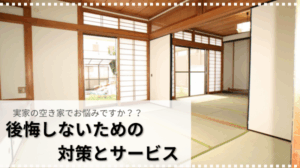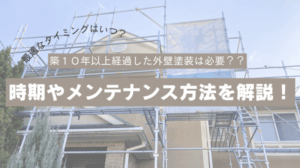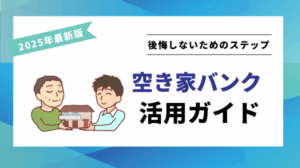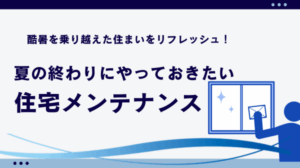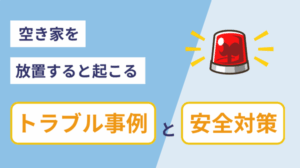近年増加している空き家。適切に管理されていない空き家は、放火や漏電などによる
火災のリスクが高まります。
実は空き家での火災は珍しくありません。人が住んでいない空き家で
なぜ火災が起きるのか。
人の気がないはずの建物が、ある日突然炎に包まれる…そんなニュースを
目にしたことはありませんか?
実は、空き家は「使われていないから安全」というわけではなく、管理の目が
届きにくいために、火災リスクが高まる危険な存在なのです。

この記事では、空き家で実際に起こった火災事例を基に、「なぜ火がでるのか」
「どう防げるのか」を解説いたします。
電気を止めなかった”うっかり”が引き金に
例えば、ある住宅では使っていない冷蔵庫をそのままにし、電気を切らず放置してしまいました。
夏場の高温でモーター部分が過熱し、さらにコンセントまわりに溜まっていたホコリに引火。
誰もいない空き家で電気火災が発生し、発見されたときには建物の大半が焼失していたのです。
老朽化した配線の危険性
電気配線は時間の経過とともに劣化し、絶縁性能が低下します。
特に湿気が多い場所や、ネズミなどの害獣が生息する場所では、配線の劣化が加速する
可能性があります。漏電は、電気エネルギーが意図しない場所に流れ出す現象で、
火花が発生し、周囲の可燃物に引火する可能性があります。

電気・ガス・水道の停止
空き家で使用していない電気はブレーカーを落とし、ガス、水道は元栓を閉めて
停止しておくことが重要です。
これにより、漏電やガス漏れによる火災リスクを減らすことができます。
また、定期的にメーターを確認し、異状がないかを確認しましょう。
メーターの数値が変動している場合は、漏電、ガス漏れ、漏水の可能性があります。
放火の標的にされやすい空き家の現状
もう一つ、重大なリスクが放火です。
管理が行き届かない空き家は、人目につきにくく、放火犯に狙われやすい傾向があります。
特に雑草が生い茂っていたり、ごみが放置されていたりする空き家は、格好の標的となります。
実際、ある地域では、何年も放置されていた住宅が深夜に放火され、
隣家にまで火が燃え広がるという被害が発生しました。
玄関のかぎが壊れたままで、内部には布団や新聞紙などの可燃物があり、結果として完全に消失する
全焼火災となったのです。
空き家の火災は、周囲の住宅や地域全体の安全を脅かす結果になります。
放火犯に狙われやすい空き家の特徴
- 雑草や草木が生い茂り、荒れた外観になっている
- ゴミや不用品が散乱し、「管理されていない」と分かりやすい
- 施錠が甘かったり、窓が割れたまま放置されている
こうした空き家では、放火犯の標的になりやすいです。

空き家の放火リスクをさげるには
定期的な清掃や草刈りを行い、防犯カメラやライトを設置するなどは効果的です。
清掃や草刈りは、空き家が管理されていることをアピールし、放火犯を抑止する効果が
あります。防犯カメラは、不審者の侵入を監視し、万が一放火が発生した場合の証拠と
なります。
さらに、地域住民との連携も重要です。
近隣住民に空き家の状況を把握してもらい、不審な人物を見かけた場合は通報してもらうように
依頼しましょう。
地域全体で空き家を見守る体制をとることで、放火リスクを大幅に低減することができます。

火災は自然災害からも起こる
空き家火災の引き金となるのは、人為的な原因だけではありません。
地震による建物の倒壊や、台風による雨漏りや浸水で電気配線がショートするなど、
自然災害がきっかけとなる火災もあります。
地震が発生すると、建物が揺れ、倒壊する可能性があります。
倒壊した建物は、電気配線やガス管を破損させ、火災の原因となることがあります。
また、台風などの強風によって、屋根が飛ばされたり、窓ガラスが割れたりする可能性
もあります。これらの被害は、雨水の侵入を招き、電気配線のショートや漏電を引き起こす
事があります。
自然災害による火災への予防対策
耐震補強や火災報知機を設置するなどの対策が有効です。
耐震補強は、建物の耐震性を高め、倒壊のリスクを低減します。
火災報知器は火災の発生を早期に検知し、迅速な非難を促します。
また感震ブレーカーの設置もおすすめです。
感震ブレーカーは地震を感知すると自動的に電気を遮断し、電気配線からの
火災を防ぎます。
自然災害はいつ起こるか分からないからこそ、「もしも」に備える意識が欠かせません。
「何もない今こそ」が対策のチャンス
空き家の火災は「自分の財産の損失」にとどまりません。
場合によっては、隣家を焼き、近隣住民を巻き込み大きな被害につながることもあります。
定期的なメンテナンスや、見守りサービスなどを活用することで、
火災のリスクを減らすことができます。
空き家を適切に管理することは、自分自身だけでなく、近隣住民の安全にも繋がります。
空き家をお持ちの方は、今一度ご自宅の安全管理を見直してみてください。